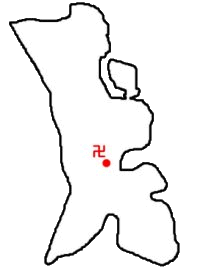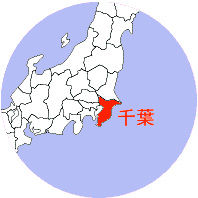 千葉県の北西部(地図で見ると左上)、水と緑と歴史の町「流山市(ながれやまし)」の市野谷(いちのや)という場所にあります。
千葉県の北西部(地図で見ると左上)、水と緑と歴史の町「流山市(ながれやまし)」の市野谷(いちのや)という場所にあります。
流山市は江戸川に面し江戸から明治にかけて水運と醸造業で大変に栄えた町です。今でいう県庁がこの地にあったことからも当時の繁栄が偲ばれます。
街の中心には赤城山という標高15メートルのお椀を伏せた形の小高い丘があって、山上には赤城神社がお祀りされています。ここはその昔、群馬の赤城山の一部が大水の際この地に流れ着いたという伝説があり、流山の地名の由来となっています。ひょっこりひょうたん島の話はこの伝説を元に作られたとかそうでないとか。
ともあれ、このように流山市民は伝説を町の名前にし、市の名前にしてしまうというおちゃめな一面を持ちます。
流山市は「赤ずきんちゃんが木の切り株に腰をかけ、たい焼きを食べているような形」をしておりますが、その赤ずきんちゃんのおなかのあたりがちょうど市野谷で、円東寺のある場所です。
※こんな大雑把な地図では分からない、といわれる方は右図をクリックして下さい。中雑把な地図が出てきます。
市野谷という地名は円東寺の門前に市がたったからとか、その昔馬の飼育をしていた代官の市野惣太夫という人が住んでいたからとか昔の話だけに諸説あります。
“イチノ”はともかく取り敢えず谷になっているのは確かで、周りの里山からの湧水が流れ込み、自然豊かな湿地帯を生み出しています。さすがにツチノコはいませんが都会ではけっして見られない動植物がのびのび暮らしています。境内ではキジが散歩してたりします。
そんなところにある延命山(えんめいざん)円東寺(えんとうじ)は元和年間(1615〜1624)創建と伝えられる真言宗豊山派の寺院です。江戸川八十八ヶ所の四十七番、六十九番札所であり、ご本尊は真言教主の大日如来さま(金剛界大日如来)をお祀りしております。
大日如来さまのご真言は【オン バザラ ダド バン】です。覚えておいて、おまいりの際はお唱え致しましょう。
また、境内からは縄文時代の竪穴式住居が多数発掘されており、数千年前から、住居に敵した場所、かつ、パワースポットであったことが分かります。

境内入り口の六地蔵さまと如意輪観音さま
ある雪の降った朝の参道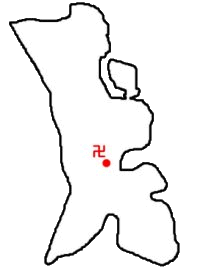

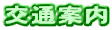
←クリック(押して)してください

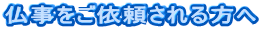
菩提寺が無く(霊園などに墓地をお持ちの方)、当寺もしくはご自宅での年回忌法要などをご希望される方、あるいは通夜・葬儀における導師を依頼しようとお考えの方は、ぜひ一度、円東寺にお越しいただき住職とお話されることをオススメいたします。
会ったことも話したことも無い、資格の有無も定かでない僧侶に、葬儀社主導もしくは電話一本で愛する家族や大切なご先祖のことを任せるのは、その家の当主の正しいあり方ではないと考えております。
また、お施主様がどのような経済状況にあろうと、お布施の額に係わらず、必ず戒名をお授けします。
次ページ
千葉県の北西部(地図で見ると左上)、水と緑と歴史の町「流山市(ながれやまし)」の市野谷(いちのや)という場所にあります。